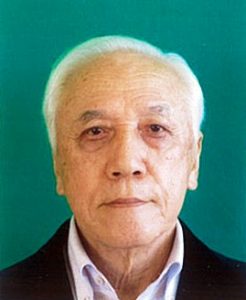ポストコロナ時代と同窓会
紀学同窓会会長 岡村周成(おかむら しゅうじょう)
会員の皆様には、平素より当会の活動にご理解とご支援を戴き誠に有難うございます。
ところで、2020年当初から爆発的に感染が拡大しました新型コロナ感染症のもと、所謂「コロナ禍」の状況が続き、日常生活も様々な制約・制限を受けることを余儀なくされました。
その間、当会の活動も理事会・評議員会及び各支部の会合等が軒並みに中止となるなど著しく制限せざるを得なくなり、関係各位に大変なご苦労・ご不便をおかけしました。
ようやく、「第8波」以降は対策の効も有り、感染状況が落ち着きはじめました。政府の感染法上の第5類への引き下げや出入国の制限の撤廃等が進み、以前の「日常」が戻りつつありますが、それと同時に「日常」の持つ意味の深さにあらためて考えさせられたことが多々ありました。
まだまだ予断を許されませんが、今後はコロナウイルスの存在を前提としたポストコロナ時代に入っていくこととなります。
従いまして、令和5年度は、当会の活動も通常に戻し、感染対策に留意した上で理事会・評議員会も3年ぶりに開催する運びとなりました。
積年の課題としては当会の組織の強化・充実が挙げられます。当会の役員を現職の方々に担っていただくこと、はかなり厳しい状況があり現実的ではありません。しかし、定年後も何らかの理由・形で仕事に就く方々も多く、本部・支部共々、無理を承知でお願いしているのが実際のところです。
また、支部として県内に8支部、県外に5支部が設置されていますが、一部には支部活動費補助金を辞退するなど、ほぼ休眠状態にならざるを得ない状況も見受けられます。
県外の支部の多くは、昭和50年の創立100周年式典を契機に紀学同窓会が再発足した際に設置されました。したがって、当時の卒業生の人脈が支部設置に大きく関与していたと推測されます。一方、現在の県外卒業生の在住分布状況を見ますと、既設の県外支部ではカバーできない空白地域が多々見られます。現規約では、支部未設置の地域では評議員を選出できず、意見が反映しづらくなっています。これらの課題解決に向けても取り組んでいきたく思いますので、HP等を活用して会員の皆様方の声をお寄せ下さい。
さて、真砂キャンパスに「奥山の根上がり松」の老樹が一本だけ威容を誇っています。この松の保全事業に当会も寄附金を拠出しています。皆様方のご理解・ご支援をお願いします。(拠出金は会費からでは無く、別途寄附された基金から支出しています)
今、和歌山大学及び教育学部におきましては、コロナ禍を乗り越えて「地域と共に歩む国立大学」としての在り方を目指して様々な改編・改革が進められています。
従いまして、当会といたしましても、新たな体制への理解に努め、支援・協力を続けて参りたいと思いますので、会員の皆様方もよろしくお願いいたします。